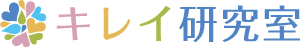スぺ100って太ってるの?メディカルダイエットについて筑波胃腸病院理事長鈴木先生にお伺いしました
近年、医師の指導や施術、投薬などを受けておこなうダイエットが注目を集めています。
効果やメリットはもちろんですが、リスクやデメリットも気になりますよね。
今回は、筑波胃腸病院の鈴木隆二先生にメディカルダイエットについてお話を伺いました。

GLPー1注射(オゼンピック・マンジャロ)
GLP-1受容体作動薬は、もともと糖尿病治療薬として開発されました。
体内の「GLP-1」というホルモンが満腹感を高め、食欲を抑えることで、自然に食事量を減らせます。
医学的な作用:
GLP-1は胃の動きを遅くし、脳に「もう食べた」という信号を送ります。
これにより、無理なく食欲が減り、摂取カロリーが減少します。
臨床試験では、平均して体重の5~15%減少が確認されています。
注意点とリスク:
副作用:吐き気、便秘、低血糖、膵炎リスク
投与中止後のリバウンドが多い
痩身目的での使用は「適応外使用」になる場合あり
医師からのアドバイス:
GLP-1注射は「食欲をリセットする補助」であり、生活習慣の改善とセットで行うことが前提です。
医師管理下で、定期検査を受けながら安全に使用しましょう。
えっ、マンジャロはダイエット注射ではない?!
標準体重以下と思えるインフルエンサーの方などが、SNSで「マンジャロで爆ヤセ」などと上げているのを見かけたことがあるという方も多いでしょう。
しかし、そもそもオゼンピック、マンジャロは痩身には医学的に使われていません(糖尿病の治療薬です)。
肥満症に適応があるのは、ウゴービとゼップバウンドという同じGLP-1でも違った薬品になります。
肥満症に適応されている薬剤でも、その適応は
「BMI≧35、またはBMI≧27かつ複数の肥満関連疾患(高血圧・脂質異常症・2型糖尿病など)を合併、かつ食事・運動で不十分な場合」
とされていて、厳格なものです。
つまりは、SNSで「細身のインフルエンサーがマンジャロを勧めている」という状況は、医療上の適応外利用を示唆しています。
美容目的の使用が問題な点として、よく医療の世界で出てくる以下の点を上げておきます。
1)適応外(エビデンス外)の投与
痩身・美容のみを目的とした使用は承認条件から外れ、安全性・有効性のバランスが検証されていません。医療倫理上も問題があります。
2)栄養不良/除脂肪量の減少
食欲低下により筋肉・骨量も落ちるリスク。
長期の健康・代謝に不利益です。
3)有害事象
消化器症状(悪心・嘔吐・便秘)、胆石・胆嚢障害、膵炎の懸念、(チルゼパチドでは)甲状腺腫瘍リスクの警告(米国ラベリング)など。
リスクに見合うベネフィットが乏しい体型では、害が上回りがちです。
4)中止後の体重再増加
中止で食欲が戻りやすく、リバウンドや体重変動の反復は健康リスクになります。
5)供給・医療資源の問題
適応のある患者さん(肥満症・糖尿病)に薬が行き渡らなくなる事態が予測されます。
スルリム注射(脂肪溶解注射)
SNSでは「脂肪を溶かして排出」「局所的に細くなる」と話題の注射。
実際は、薬剤を注入して脂肪細胞を破壊し、体内で代謝・排出させるという仕組みです。
医療的な根拠:
主成分の「デオキシコール酸」は米国FDAで顎下脂肪減少にのみ承認されています。
全身や体幹への使用は自由診療(エビデンス不足)のため、効果に個人差があります。
リスク:
腫れ、内出血、硬結、神経障害、感染など。
「溶解した脂肪が尿として出る」という説明は誤りです。
医師からのアドバイス:
信頼できる医療機関を選び、成分・濃度・施術実績を確認しましょう。
過度な期待を持たず、「部分的なボリューム調整」として捉えるのが現実的です。
脂肪冷却(クールスカルプティングなど)
「寝ているだけで痩せる」と注目を集める施術。
皮下脂肪を冷却し、脂肪細胞をアポトーシス(自然死)させる仕組みです。
医療的根拠:
FDA承認済みで、局所的な脂肪減少効果が確認されています。
ただし、体重そのものを減らす目的には向いていません。
リスク:
冷却による皮膚ダメージ。
ごく稀に「反跳性脂肪過形成(脂肪が逆に増える)」が起こることがあります。
医師からのアドバイス:
冷却施術は「体のラインを整える補助」として有効。
全身痩せではなく、部分シェイプ向けと理解することが大切です。
脂肪吸引手術
脂肪細胞を直接除去する方法で、確実な部分痩せが可能です。
1回の手術で数リットル単位の脂肪を除去することも可能。
医療的根拠:
吸引した脂肪は再生しないため、局所的な変化は確実です。
しかし、残った脂肪細胞が肥大すればリバウンドは起こりえます。
リスク:
たるみ・凹凸、出血、感染、脂肪塞栓など。
手術者の技術による差が大きい点も重要です。
医師からのアドバイス:
脂肪吸引は「ラインを作る治療」であり、体重減少を目的とするものではありません。
術後ケアと生活改善を並行して行うことが成功の伴です。
脂肪燃焼薬・痩身薬(飲み薬)
「飲むだけで脂肪が燃える」という薬は存在しません。
日本で認可されているのは、食欲抑制薬(サノレックス)・脂肪吸収抑制薬(オルリファスト)の2種類のみです。
医療的根拠:
どちらも医師の処方とモニタリングが必須。
一方で、海外製「ファットバーナー」などは、成分不明・副作用(肝障害・心拍上昇)のリスクが高いものも多いです。
医師からのアドバイス:
脂肪燃焼薬は「太りにくくする補助」と考えましょう。
サプリに頼らず、まずは食事・運動・睡眠の基盤づくりが最優先です。
ふくらはぎ神経遮断(ボトックス注射)
ボトックスを筋肉に注入してm神経伝達を一時的に抑えることで筋肉の張りを和らげる施術です。
医療的根拠:
ふくらはぎの筋肉(腓腹筋など)を一時的に萎縮させ、見た目をスッキリさせる効果が確認されています。
脂肪を減らすわけではありません。
リスク:
過剰投与で歩行バランスの崩れ、筋力低下、違和感。
効果は3~6か月程度で切れ、定期的な継続が前提です。
医師からのアドバイス:
「筋肉の張りをやわらげる美容的補助」としての使い方はあるのかもしれません。
スポーツをする方は注意が必要です。
医師から見た「医療ダイエット」」全体評価
医療ダイエットは、「生活習慣の改善を支えるツール」として非常に有用です。
ただし、薬や施術だけで完結するものではありません。
医学的根拠や科学的根拠がある方法も多いが、万能ではないです。
また、効果・安全性には個人差が大きいでしょう。
医師管理下で、長期的な健康維持を目指すことが本来の目的です。
医療ダイエットは「スタートライン」に過ぎません。
本当のゴールは「太りにくい生活習慣の確立」です。
「スペ100はデブ?」SNS文化と適正体重
「身長-体重=〇〇」という「スペック数」で体型を判断する文化がSNSで広がっています。
たとえば「スペ100=太い」といった風潮ですが、これは医学的に誤りです。
医療的根拠:
BMI=体重(kg)÷身長(m)²で一般的には18.5~24.9が正常範囲とされています。
160cm・60kg(=スペ100)はBMI23.4で標準体重です。
つまり、「スペ100は健康的な範囲」に含まれます。
医師からのアドバイス:
数字よりも重要なのは、
・筋肉量
・体脂肪率
・ホルモンバランス
・体調の安定
です。
「スペック」より「健康美」を重視する時代にシフトしていきたいですね。
まとめ
医療ダイエットには、確かに科学的根拠のあるものが多くあります。
しかし、それらはすべて生活習慣のサポート手段であり、魔法ではありません。
医師としてお伝えしたいのは
「一時的に痩せるより、健康的に『維持できる』ことの方が、何倍も価値がある」ということです。
SNSの数字よりも、自分の体調・笑顔・自信を大切にしてもらいたいです。
医療の力を上手に取り入れながら、「健康的にキレイ」を叶えるのが理想のダイエットと考えます。
[執筆者]

鈴木隆二先生
筑波胃腸病院理事長
日本消化器内視鏡学会専門医
日本外科学会専門医
全ての患者の健康を第一に考え、日々最新の医療技術を提供しています。
理事長として筑波胃腸病院と千葉柏駅前胃と大腸肛門の内視鏡日帰り手術クリニック健診プラザをメインに運営し、消化器疾患の早期発見と治療、予防に力を入れています。