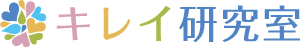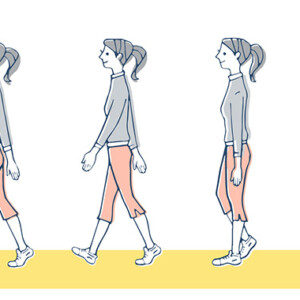毎日ぐっすり眠れない。睡眠の質を向上させる方法についてクリニック院長の菊池先生にお伺いしました
涼しさを感じられるようになり、ようやくぐっすり眠れる・・・と思っていたのに、なかなか寝付けなかったり、寝ても疲れが取れていなかったり。
いい睡眠を取るには、どうすればいいの?
今回は、用賀きくち内科肝臓・内視鏡クリニック院長の菊池真大先生にお話を伺いました。

日照時間が低下する秋は睡眠の質が低下しやすいって本当?
猛暑がようやく過ぎ去り、朝晩の空気に秋の気配を感じるようになりました。
私たちの身体も「夏から秋」へと静かに移行しています。
でも最近、なんとなく眠りが浅い、朝起きても疲れが抜けない、気力が湧かない・・そんな感覚、ありませんか?
この時期の睡眠について考えてみます。
秋になると日照時間が短くなり、太陽の光を浴びる時間が自然と減っていきます。
実はこの「光の量」が、私たちの睡眠に大きく関係しているのです。
太陽光を浴びることで分泌される「セロトニン」は、心を安定させる『幸福ホルモン』であり、夜になると「メラトニン」という『眠りのホルモン』に変化します。
ところが、秋は光の量が減るため、セロトニンの分泌が少なくなり、結果としてメラトニンも不足しがちになります。
その影響で、眠気のリズムが乱れたり、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりするのです。
また、朝晩と日中の気温差が大きく、体温調節に負荷がかかることで、自律神経が乱れます。
交感神経が過剰に働き、リラックスすべき副交感神経がうまく切り替わらず、寝つきが悪くなるわけです。
他にも、夏に冷たいものを摂りすぎた影響で、腸が冷え、セロトニン生成が低下してしまい、腸内環境の悪化が『眠りホルモン』の材料不足につながる可能性もあります。
夏の疲れによる秋バテが秋の睡眠の質を悪化させる?
近年の気象変動により、夏の猛暑の中でクーラーのある室内生活が長い傾向にあります。
その結果、体力が落ちている状況で秋を迎え、例年にはない体調変化を感じている方も多いと思います。
夏の高温多湿や熱帯夜、冷房による寒暖差などで、交感神経が過剰に働き、秋になっても副交感神経への切り替えがうまくいかず、寝つきが悪く、眠りが浅くなるといった不調が現れます。
まず「朝の光を浴びること」が大切です。
起きてすぐにカーテンを開けて、10分でも外の光を浴びるだけで、セロトニンの分泌が促され、体内時計が整います。
さらに、軽い有酸素運動やストレッチ、筋トレなど夏には出来なかった外での運動を行うことで、セロトニンが活性化し、夜のメラトニン生成につながります。
夜はぬるめのお湯で入浴を。
入浴後に体温がゆっくり下がるタイミングで、自然な眠気が訪れやすくなります。
しっかり眠るのに食べておくべき食材とは
秋の味覚には、眠りを助ける栄養素がたっぷり。
中でもおすすめは「秋刀魚」。
セロトニンの材料となるトリプトファンや、脳の働きを整えるEPA・DHAが豊富です。
また、しめじ・舞茸・しいたけなどのキノコ類は、ビタミンB群が豊富で、疲労回復や神経の安定に効果的。秋の食卓にぜひ取り入れたいですね。
ただし、果物の摂りすぎには注意。
林檎・葡萄・柿など、秋の果物には果糖(フルクトース)が多く含まれており、過剰に摂ると体脂肪の蓄積や脂肪肝のリスクが高まることも。
秋の味覚は甘さに惹かれすぎず、適切な量をほどほどに楽しみましょう。
秋は急激な気温変化で、心も体も乱れやすい季節。
だからこそ、私たちの身体も「整える」ことが大切です。
眠りの質を高めることは、心と体の回復だけでなく、日々のパフォーマンスや人との関わりにも影響します。
秋の澄んだ空気とともに、眠りの質も、心の調律も、少しずつ整えていきましょう。
※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。
執筆者

菊池真大先生
用賀きくち内科肝臓・内視鏡クリニック院長
慶應義塾大学医学部卒業
東海大学医学部客員准教授
米国ペンシルバニア大学消化器内科元博士研究員
日本アルコールアディクション医学会理事
日本総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内視鏡学会専門医、日本人間ドック健診専門医、日本病態栄養学会専門医、日本抗加齢医学会専門医
2024年秋、メタボとロコモを同時予防管理する未来志向型クリニックを東京・用賀の地に開業。
用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック
https://www.youga-naika.com/