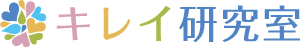夏バテになりやすい人・なりにくい人はいるの?クリニック院長の柏木宏幸先生にお話を伺いました
暑い日が続き、毎日疲れを感じてませんか。
「夏バテかな・・・」と思う方も多いでしょう、ですが夏バテって具体的には何を指すのでしょうか?
今回は、夏バテやその原因、対処法について、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院院長の柏木宏幸先生にお話を伺いました。

夏バテって、具体的には何?どんな症状がある?
夏バテとは、夏の高温多湿な環境により自律神経の調整機能が乱れた結果、引き起こされる体調不良です。
自律神経というのは、体内の活動を維持するために無意識に機能しており、環境によって自律神経の調整機能が乱れるとさまざまな症状が起こります。
具体的には
・倦怠感
・食欲不振
・疲労感
・睡眠障害
・胃腸の不調
などが起こります。
どうして夏バテになるの?
気温が高くなると、人間は体温が高くなりすぎないように発汗して体温を調整します。
この体温を調整するのが自律神経です。
特に、夏には冷房を効かせた室内と室外との気温差が大きくなることから、その激しい気温差を繰り返すことで、体温の調整を行う自律神経のバランスが崩れやすくなります。
また汗をかくことによる、水分・塩分不足も夏バテを起こしやすくなる原因となります。
夏バテになりやすい人・なりにくい人はいるの?
日頃から不規則な生活をしている人は起こりやすくなります。
まず自律神経というのは交感神経と副交感神経に分けられます。
交感神経はアクセルの役割、副交感神経はブレーキの役割とされています。
交感神経は、日中の活動している時に有意になり、身体活動を高める神経です。
心拍数増加や血圧上昇などに作用し、集中力を高める作用もあり、腸の運動を低下させます。
副交感神経は睡眠時やリラックスした時に優位になる心身を休める神経であり、血圧を下げる、心拍数を下げる、呼吸を落ち着かせる、消化や免疫機能を高めるなどの作用があります。
通常の生活では日中は交感神経が優位に働き、夜間は副交感神経が優位になるのですが、昼夜逆転など不規則な生活により、自律神経のバランスが崩れることで夏バテの原因となります。
その他、睡眠不足・運動不足、栄養が偏った食事を続けている方など自律神経の調整に必要な要素が不足すると、夏バテになりやすくなります。
一方、規則正しい生活やバランスの良い食事を心がけている方は夏バテになりにくくなります。
クーラーの効いた涼しいオフィスで仕事しているなら心配ない?
夏季にクーラーの効いた涼しい部屋と外気温の差が5℃以上あると、自律神経の乱れに繋がります。
25~27℃にクーラーを設定していた人と比べ、22~24℃に設定している人の方が、倦怠感や頭痛症状を起こす割合が高くなったとの報告があります。
また、1日中クーラーの効いた部屋にいる人は外出時に強い倦怠感を感じやすいとの報告もあります。
ですので、室内と外気温の差が5℃以内であることが望ましく、夏バテのリスクを低下させる設定温度は25~28℃が目安とされ、定期的に換気をすることが最適です。
また冷気が直接、身体に当たらないことが望ましいです。
体だけでなくメンタルにも影響する?
夏バテは身体だけではなく、メンタルヘルスにも影響します。
自律神経の乱れにより、やる気の低下やイライラしやすくなること、心身の疲労などの症状が起こります。
夏バテによる疲労や体力低下によっても、精神的な不調に繋がることもあります。
メンタルヘルスが悪化することで、夏季うつ病という更に深刻な集中力の低下や、睡眠障害、気分の低下などの原因にもなります。
肌あれの原因にもなる??
肌や髪にも影響します。
夏バテによる食欲不振、冷房による冷え・血行不良により、皮膚や頭皮、髪の栄養不足にも繋がり、肌荒れや育毛環境にも影響します。
夏という季節は、紫外線により肌や髪も痛みやすく、海水やプールの塩素によっても毛髪が傷むことで、変色や抜け毛といったトラブルにも繋がります。
紫外線はくすみ・シミ・肌のたるみの原因であり、エアコンによる肌の乾燥はシワの原因となります。
紫外線や乾燥は抜け毛、フケ、髪のパサつきにも影響します。
また、皮脂や汗の分泌過剰による毛穴の詰まりも髪の成長の妨げとなります。
予防方法は?
夏場での予防方法は、
1.十分な睡眠と休息、
2.栄養バランスの良い食事(特にビタミンやミネラル)
3.こまめな水分補給
4.(室内で)軽い運動を取り入れる
5.クーラーの温度管理を適切に
などが重要です。
クーラーに関しては、室内と外気温の差が5℃以内、夏バテのリスクを低下させる設定温度は25~28℃が目安とされ、定期的に換気することが最適です。
冷気が直接身体に当たらないことが望ましく、扇風機を壁に向かって使用することによって風が直接体にあたらないようにして、柔らかい風に変化することで室内の空気を効率的に循環させることも良いとされています。
また就寝中にクーラーが効きすぎ、体温を下げ過ぎると眠りが浅くなることが分かっており、その結果、睡眠の質が低下して翌日の疲労感が増すということも明らかとなっています。
夜間のクーラーの設定としては27~28℃の弱冷房運動・自動運転が良いでしょう。
タイマー設定(3~4時間)は、朝の気温や湿度が高い場合に起床時には室内の温度も上昇してしまうことから、タイマー設定より「つけっぱなし」にした方が快適な睡眠に繋がったとの検証もされており、温度を下げ過ぎないように注意して夜間は「つけっぱなし」にすることを検討してみましょう。
どんな食事(食材・栄養素など)がおすすめ?
1日3食、エネルギー源となる主食(炭水化物)、身体の元となる主菜(たんぱく質)、からだの調子を整える副菜(ビタミン、ミネラル食品)をバランスよく摂取していただくことが大切です。
朝食を食べない方もいると思いますが、朝から体温を上げ代謝をよくすることで、疲れにくい身体をつくるためにも朝食を食べることをお勧めします。
1)たんぱく質
筋肉疲労を解消させる効果、体力温存効果があります。
たんぱく質は肉・魚・卵・納豆、豆腐などの大豆製品、乳製品に含まれます。
2)ビタミンB群
ビタミンB群、特にビタミンB1やビタミンB2は麺類など穀類に多く含まれる炭水化物をエネルギーに変える働きをしてくれます。
豚肉、うなぎ、納豆・豆腐などの大豆製品、枝豆、卵などに含まれます。
例えば、豚しゃぶサラダや豚の生姜焼きなどがお勧めです。
3)ミネラル
夏バテでみられる、倦怠感(だるさ)は汗で失われるカリウム不足も原因とされます。
野菜や果物にカリウムは多く含まれています。
4)ビタミンC
紫外線のダメージによる活性酸素を除去したり、疲労回復の効果があります。
野菜や果物などに多く含まれます。
5)クエン酸
クエン酸は酸味成分を含み、食欲増進や疲労回復の効果が期待されます。
唾液と胃酸の分泌が促進され、胃が活発に動き、食欲増進に繋がります。
疲労や肥満の原因となる乳酸や脂肪を分解・燃焼することで疲労回復の効果が期待されます。
オレンジやレモンなどの柑橘類、梅干し、酢などに含まれます。
夏は冷たい飲み物や食べ物が好まれがちですが、野菜たっぷりのスープやみそ汁などを1品、食事の最初に食べることで胃腸にとっても非常によいです。
胃腸の調子が悪いときには、胃腸に負担の少ない食事がお勧めです
消化に良く、温かいものとしてはお粥、うどんなどが挙げられます。
そうめんも消化が良いですが、単品ではなく野菜や肉などと一緒に摂って頂くと良いでしょう。
夏バテのときに摂らない方がいいものってある?
1)過度な冷たいもの
胃腸を冷やすような冷たい飲み物・食べ物の過度な摂取は控えた方が良いとされています。
2)炭水化物に偏りすぎること
暑いときは、そうめんや蕎麦などで済ませてしまうことも多いですが、麺類だけでは栄養バランスが偏りやすく、栄養が偏らないように炭水化物に偏ったものは控えたほうがよいです。
3)消化の悪いもの
胃腸症状であったり、疲労回復の視点で夏バテの時は消化の悪いものは控えた方が望ましいでしょう。
消化の悪いものとしては、
・脂質が高いもの(ピザ、揚げ物、脂身の多い肉など)
・生もの(刺身、生肉、お寿司など)
などが挙げられます。
たかが夏バテと思わないで!受診する必要があることも?
夏バテに関しては漢方薬での治療もありますし、脱水がひどい場合には点滴なども相談できます。
胃腸の症状に関しても胃薬や整腸剤なども処方されることがあります。
発汗による体温調節がうまく働かなくなると、体内に熱がこもり、熱中症という状態になります。
熱中症は失神や頭痛、吐き気、嘔吐、意識障害などの症状をきたし、命に関わるリスクになります。
症状や命に関わるかという点において、夏バテと熱中症は異なりますが、症状が酷い場合には熱中症になりかけている可能性があるため医療機関へ受診して頂くことをお勧め致します。
特に脱水症状や極端な疲労感がある場合は早めに受診してください。
[著者]

柏木宏幸先生
総合内科専門医・消化器病専門医
池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院 院長
埼玉医科大学卒業
東京女子医科大学消化器内科にて助教となり、複数の医療機関で経験を積む。
2023年に現クリニックを開院。胃がん・大腸がんの早期発見と内視鏡検査の普及を目指し、健康診断や消化器疾患、一般内科の診療を幅広く実践。
また、YouTubeチャンネル池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック(@HKa-wb4jw)を通じて医療知識や内視鏡検査の重要性を発信中。
池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院
https://www.ikebukuro-cl.com