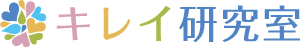糖質制限したらダイエットできる?メリット・デメリットについてクリニック院長澤口先生にお伺いしました。
糖質制限や糖質オフといった言葉も一般的になってきています。
健康やダイエット目的で、糖質の摂取量を気にされている方も多いのではないでしょうか。
今回は、糖質制限ダイエットやケトジェニックダイエットの仕組みやメリット・デメリットについて、豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック院長の澤口達也先生にお話を伺いました。

糖質制限ダイエットとは?:基本的な仕組み
糖質制限ダイエットは、糖質(炭水化物)の摂取を減らし、脂肪とタンパク質を多めに摂取することで、体脂肪を燃焼しやすくするダイエット法です。
糖質を減らすことで、体は糖の代わりに脂肪をエネルギーとして使うようになります。以下の流れで脂肪が燃焼されやすくなります。
1.糖質制限でブドウ糖が不足
2.グリコーゲンを分解して一時的にブドウ糖を供給(約24時間)
体内で糖分(グルコース)が不足すると、血糖値を維持するために、まず肝臓や筋肉に蓄えられているグリコーゲンがグルコースに分解され利用されます。
しかし、体内のグリコーゲンは18~24時間程度で枯渇してしまいます。
3.糖新生が始まるが、ブドウ糖の供給が間に合わなくなる
糖新生(とうしんせい)とは、体内の糖以外の物質(アミノ酸、乳酸、グリセロール)から新しくグルコースを作り出す代謝プロセスのことです。
主に肝臓(その他腎臓)で行われます。筋肉から糖新生のために必要な材料(アミノ酸や乳酸)が供給されるため、筋肉の分解が進みやすくなります。
4.脂肪を分解し、脂肪酸とグリセロールを放出
糖新生だけではエネルギーが不足するため、体はエネルギー源として脂肪を分解(脂肪酸とグリセロールに分解)します。
なお、グリセロールは糖新生に使われますが、供給量が少ないため、脂肪酸の利用がメインとなります。
5.脂肪酸からケトン体が生成される
肝臓で、脂肪酸を原料としてケトン体(アセト酢酸、βヒドロキシ酪酸、アセトン)が生成され、血流を通じて全身(脳、筋肉、心臓)のエネルギー源として使用されます。
糖質制限の分類
糖質の摂取量を制限するのが糖質制限ですが、その度合いにより、以下の3つに分類されます。
極端に糖質を制限したダイエットは、前述の通り、ケトン体が生成されやすくなるため、ケトジェニックダイエットと呼ばれます。
1.ゆるやかな糖質制限(ロカボ)
1日の糖質摂取量:70〜130g
目標:体重維持、健康改善
主食の制限:白米・パン・麺類の量を減らし、玄米や低糖質パンに置き換える
適している人:糖質を減らしたいが、無理なく続けたい人
2.標準的な糖質制限
1日の糖質摂取量:50〜100g
目標:ダイエット、体脂肪減少
主食の制限:主食はほぼなし(1日1回少量)
適している人:体脂肪を減らしたいが、極端な制限はしたくない人
3.極端な糖質制限(ケトジェニックダイエット)
1日の糖質摂取量:50g以下
目標:脂肪燃焼、ケトーシス状態の維持
主食の制限:主食は完全になし
適している人:短期間で体脂肪を減らしたい人、糖質を徹底的に制限できる人
糖質制限ダイエットは、50~130g程度に糖質摂取量を抑え、脂肪を適量取りながら、ゆっくりと脂肪燃焼を促すことを目的として行われます。
急激なダイエットではなく、ゆるく続けたい方や、糖尿病を予防したい方に向いています。
そして、ケトジェニックダイエットは、1日の糖質摂取量を50g以下に抑え、主なエネルギー摂取源を脂肪とすることで、ケトーシス状態をつくって脂肪を燃焼させる目的でおこなわれます。
短期間で成果を出したい方や、自己管理を徹底できる人に向いています。
糖質制限の方法
食物においてエネルギー(熱量、カロリー)を持っているのは、主に3大栄養素(炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質)です。
総エネルギー(総カロリー)は確保したまま、内訳として、炭水化物(糖質)を減らし、タンパク質や脂質の摂取量を増やしていきます。
1.食事の主な構成
糖質制限では、以下のような栄養バランスを意識すると効果的です。
栄養素 推奨割合 主な食品例
糖質 10〜30% 玄米、オートミール、糖質オフ食品
タンパク質 20〜30% 肉、魚、卵、大豆製品
脂質 50〜70% オリーブオイル、ナッツ、アボカド、チーズ
2.高糖質食品
糖質制限では、以下の食品の摂取を控えます。
・白米、パン、麺類(ラーメン・パスタ)
・じゃがいも、さつまいも、とうもろこし
・砂糖、はちみつ、果物のジュース
・菓子パン、ケーキ、アイスクリーム
・ビール、日本酒、甘いカクテル
3.食べてもOKな低糖質食品
糖質制限中でも食べられる食品を選ぶことが重要です。
・肉類(牛・豚・鶏・羊など)
・魚介類(サーモン、マグロ、イワシ、貝類、イカ、エビ、タコ)
・卵(ゆで卵、オムレツなど)
・大豆製品(豆腐、納豆、おから、豆乳)
・葉物野菜(ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー)
・チーズ、ナッツ類(アーモンド、くるみ)
・オリーブオイル、MCTオイル、アボカド
※どうしてもお酒を飲みたい場合、蒸留酒(ウイスキー、ブランデー、焼酎、ジン、泡盛)を選ぶ
糖質制限のメリット・デメリット
<メリット>
・体脂肪が燃えやすくなる
・血糖値が安定し、糖尿病予防にもなる
・空腹感が少なく、間食が減る
・短期間で体重が減少しやすい
・糖尿病やアルツハイマー予防の可能性がある
<デメリット>
・極端な制限は、筋肉量の減少や体調不良を引き起こす可能性がある
・脂質過多による消化不良や下痢のリスク、食物繊維不足による便秘のリスク
・低血糖のリスク(特に糖尿病治療中の方は注意)
・最初の体重減少は「脂肪」ではなく「水分」
・最初の数日間、「ケトフル(倦怠感・頭痛・吐き気)」が起こる可能性がある
・長期間続けると、脂質過多による動脈硬化リスクが高まる可能性がある
体重減少に関しての留意事項
糖質制限やケトジェニックダイエットを始めると、多くの人が「最初の1週間で2〜3kg減った!」と実感します。
しかし、この減少は脂肪が燃焼したわけではなく、体内の「グリコーゲン」と「水分」が減ったことが主な理由ですので注意しましょう。
グリコーゲンは、肝臓や筋肉に蓄えられた「糖」の一種で、体のエネルギー源になります。
糖質を制限すると、まずこのグリコーゲンと水分が体から抜けます。その結果、短期間で体重が減るのです。
体重減少の内訳
・最初の1週間で減るのは水分(脂肪ではない)
・2週間目以降から本格的に脂肪が燃焼し始める
・水分が抜けた後は、減量のペースがゆっくりになる
したがって、「最初の体重減少が大きい=脂肪が落ちた」とは限らないことを理解しておくことが大切です。
低血糖のリスクと医師との相談の重要性
糖質制限やケトジェニックダイエットでは、血糖値が低くなりすぎて低血糖症状(めまい・冷や汗・倦怠感・動悸)が出ることがあります。
糖尿病の薬を服用している方、インスリンやGLP-1受容体作動薬といった注射薬を使用中の方は注意が必要です。
特にSGLT-2阻害薬という種類の薬剤を使用されている方は、ケトアシドーシス(ケトン体過剰になることによって血液中の酸塩基平衡が酸性に傾いた状態)になり、重篤な病態を引き起こす危険性もあります。
また、代謝疾患や肝機能障害、腎機能障害、心機能障害がある場合にも糖質制限時に前述の反応が見られないこともありますので、現在、何らかの疾病の診断を受けている方や治療中の疾患がある方は必ず医師に相談の上、糖質制限の可否を判断するようにしてください。
薬の調整が必要になることもあり、自己判断で極端な制限を行うと健康を害するリスクがあります。
まとめ
糖質制限やケトジェニックダイエットは、適切に行えば体脂肪燃焼に効果的ですが、リスクやデメリットもある特殊なダイエット方法です。
ゆるやかな糖質制限以上の糖質制限やケトジェニックダイエットを自己判断で進めることはおすすめできません。
健康状態に応じた注意が必要であり、特に持病のある方は医師と相談の上で実施しましょう。
[執筆者]

澤口達也先生
医師、医学博士。
豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック院長。
糖尿病専門医として、日々、糖尿病や肥満症、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の患者さんの診療に従事し、食事指導や運動指導で数多くの方の減量を成功させている。
自身でも様々な食事療法やトレーニングを実践しており、過去にはアスリートフードマイスターや加圧トレーニングインストラクターの資格を取得。
また現在、健康スポーツ医、格闘技イベントでのリングドクターとしても活動している。
豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック
https://sawagucci.com/