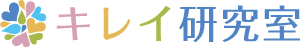内科医の視点で見た「疲労」とは?仕組みと対処をクリニック院長の澤口先生が解説!
きちんと眠っているはずなのに疲れが取れない・・・。
いつも体や頭が重い気がする・・・。
こんな悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、慢性的な疲労について、豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック院長の澤口達也先生にお話を伺いました。

内科医の視点で見た「疲労」とは?!
疲労は痛みや発熱と並ぶ「生体アラーム」です。
寝ても疲れが抜けない、休日に寝だめしても余計につらい、常に体が重い…そんなときは、睡眠・自律神経・栄養・メンタル・筋骨格といった複数要因が重なっていることがほとんどです。
内科医の視点で、仕組みと対処を解説致します。
1.寝てもすっきりしない理由
睡眠にはレム睡眠(浅い睡眠)とノンレム睡眠(深い睡眠)がありますが、年齢とともにノンレム睡眠の割合は減り、睡眠が浅くなります。
深睡眠の減少は脳と体の回復力低下に直結します。
平日の睡眠不足が「睡眠負債」として蓄積し、入眠時刻や起床時刻が日々ぶれると、体内時計が乱れ夜の眠りが浅くなります。
さらに、過度なアルコール摂取や仕事や家庭のストレスで交感神経優位が続くと、就寝中も脳が休まらず、朝のけだるさが残ります。
鍵は睡眠の「量」だけでなく「質」と「規則性」です。
また、よくいびきをかく方は睡眠時無呼吸症候群という病気が背景に隠れているかもしれません。
睡眠時間を確保しているつもりでも、疲れが取れない、日中の眠気があるという場合には医療機関受診も検討しましょう。
2.休日の寝だめが逆効果なわけ
起床時刻が平日と2時間以上ずれると、体内時計に「時差」が生じます。
また、必要以上に長く寝て深い眠りの途中で目覚めると、強い眠気やぼんやり感が残ります。
一日中ゴロゴロして血流が滞ることも倦怠感の原因になりえますので、休日こそ平日と近い時刻に起き、朝日を浴びて軽く体を動かすことが、休み明けのだるさ対策になります。
3.「一生抜け出せない気がする」慢性疲労の正体
慢性疲労は、自律神経の乱れ、エネルギー不足、酸化ストレス、筋骨格のこわばり、メンタル要因などが相互に悪循環した状態です。
背景に病気(貧血、甲状腺疾患、肝臓・腎臓・心臓疾患、持続感染、糖尿病、うつ病など)が潜む場合もあります。
以下の症状があれば受診を推奨します。
・発熱や異常な発汗
・体重増加や体重減少
・浮腫みが数日間続く
・便秘、下痢、血便、黒色便など便の異常
・多飲(水を飲み過ぎてしまう)や 口渇(水分をとってても口腔内の乾燥を感じる)
・多尿
・立ち眩みや動悸、息切れ
・月経異常、脱毛症状
・6か月以上続く強い倦怠感が休息で改善しない
・気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、意欲の低下。リフレッシュしても改善しない。
上記の様な場合には、医療機関では身体診察や血液検査等で原因を絞り込み、必要な治療と生活調整を組み合わせます。
4.メンタル要因が疲労を強める仕組み
慢性的ストレスは交感神経とストレスホルモンの過活動を招き、睡眠の質を落とし、炎症反応を高めて痛みや倦怠感を助長します。
不安が強いと体は常時「興奮状態」となり、心拍・呼吸・筋緊張が増えエネルギー消耗が進みます。
うつ病では神経伝達とストレス応答系の調節異常から、十分休んでも回復しにくい強い倦怠感を自覚します。
不眠や抑うつが強いときは心療内科・精神科に相談しましょう。
「なんか疲れが取れない」
「いつもだるい」
と思っても、その原因はさまざま。
「疲れなんて、しっかり寝れば治る!」
とは限りません。
疲労以外の症状やメンタルに関する要因がある場合は、医師にご相談ください。
[執筆者]

澤口達也先生
医師、医学博士。
豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック院長。
糖尿病専門医として、日々、糖尿病や肥満症、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の患者さんの診療に従事し、食事指導や運動指導で数多くの方の減量を成功させている。
自身でも様々な食事療法やトレーニングを実践しており、過去にはアスリートフードマイスターや加圧トレーニングインストラクターの資格を取得。
また現在、健康スポーツ医、格闘技イベントでのリングドクターとしても活動している。
豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック
https://sawagucci.com/