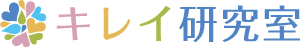運動を活用して疲れとサヨナラ!慢性疲労の解決法についてクリニック院長の澤口先生にお伺いしました。
「どうやっても疲れが取れない・・・!」
さまざまな原因で起こる慢性疲労。
どうやったら疲労感とさよならできる?!
今回は、慢性疲労の解決方法について、豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック院長の澤口達也先生にお話を伺いました。

慢性疲労から抜け出すための生活習慣リセット
お話ししたように、疲労感の原因はさまざまに考えられますが、まずは生活習慣を整えてみましょう。
1)睡眠衛生
就寝・起床時刻を一定に。
寝室は暗く静かに、就床90分前のぬるめ入浴、就床1時間前はテレビやスマートフォンの画面を見ないこと。
朝はカーテンを開け日光を浴びるようにしましょう。
2)アクティブレスト
疲れているほど「軽く動く」。
通勤を早歩きに、階段を使う、昼休みに5分歩く、夜はストレッチ。
3)リラクゼーション
深呼吸、ハーブティーやアロマ、入眠前は同じ順番のルーティンで身体を慣らしましょう。
4)水分・電解質の適度な摂取
のどの渇きの有無にかかわらず、こまめに水分を摂りましょう。
発汗が多い日は電解質も意識。
5)嗜好品
カフェインは午後早めの時間まで。
アルコールは睡眠の質を下げるため「寝酒」は避けること。
運動と筋トレの活用法
思いっきり身体を動かすことで疲労が改善することもあります。
運動することで「血流改善と代謝効率アップ」「睡眠の質向上」「筋骨格の負担軽減」が期待できます。
おすすめな頻度と強度
・有酸素運動は週150分を目安(会話ができる強度の早歩きなど)
・レジスタンス運動(筋トレ)は週2~3回、翌日に残らない負荷で大筋群を中心に
・運動未経験なら週1回10~15分程度から開始し徐々に頻度や運動時間を増やしていく
できるところから始めてみましょう。
食事と栄養(疲れに効く土台づくり)
栄養が不足していても疲労の原因となります。
基本は「主食・主菜・副菜」をそろえ、栄養の偏りや極端な制限を避けることが大事です。
1)タンパク質
筋・酵素・ホルモンの材料となる栄養素です。
毎食、肉・魚・卵・大豆・乳製品のいずれかを確保することが大切です。
とくに、朝食のタンパク質はその日のパフォーマンスを支えるもの。
しっかり摂取しましょう。
2)ビタミンB群(特にB1)
糖代謝に必須。
豚肉、うなぎ、豆類などに含まれています。
にんにく・玉ねぎの成分と合わせると吸収が上がることが分かっています。
3)鉄
酸素運搬の要。
特に、月経がある人は不足しやすいです。
レバー、赤身肉、カツオ・マグロ、ほうれん草、貝類に多く含まれます。
ビタミンCを一緒に摂ることで吸収促進されます。
4)ビタミンC
抗酸化と鉄吸収補助に働きます。
柑橘、キウイ、イチゴ、パプリカ、ブロッコリーなどの果物や野菜に多く含まれます。
こまめに摂ることが大切です。
5)クエン酸
疲労を回復する効果が期待できるので、食欲が落ちる時の梅おかゆは理にかなっています。
柑橘、梅、酢の物などに含まれています。
6)マグネシウム
酵素反応を支える働きがあります。
ナッツ、豆類、海藻、玄米、バナナなどに含まれています。
間食は素焼きナッツが便利なので、デスクなどに常備するのもおすすめです。
医療的アプローチ(受診時のチェックと治療の考え方)
疲労を主訴に医療機関を受診された場合、必要に応じて検査を行います。
血液検査
貧血、甲状腺機能、肝・腎機能異常、血糖異常、炎症反応、ミネラル欠乏の有無など。
必要に応じて睡眠障害、抑うつ、不安のスクリーニングを行います。
肥満やいびきがある場合には睡眠時無呼吸症候群が背景に隠れていないかもチェックします。
治療
原因疾患があればその治療が最優先となります(例:鉄欠乏性貧血の鉄補充、甲状腺機能低下症の甲状腺ホルモン補充など)。
睡眠障害が強いときは短期的な薬物療法を併用しながら、睡眠衛生の是正を平行して行います。
漢方薬を補助的に用いることもありますが、まずは生活の土台を整えることが基本方針となります。
今日から始める3ステップ(実行計画)
1)起床時刻を固定し、朝の光を浴びる(休日も±1時間以内)。
2)10~15分程度の歩行かストレッチを。就寝前はテレビやスマートフォンの画面をオフにする。
3)毎食タンパク質を確保し、鉄とビタミンCを意識。水分はこまめに摂取する。
これだけでも、1~2週間で日中のだるさや睡眠の質に変化が出る方が多いはずです。
改善が乏しい、もしくは気になる症状がある場合は、無理せず医療機関で原因を確認しましょう。
おわりに
疲労は「気合い」では解決しません。
仕組みを理解し、睡眠・運動・栄養・メンタルの各レバーを少しずつ動かすことが、慢性的な倦怠感から抜け出す最短ルートです。
完璧を目指さず「できることから」を合言葉に、今日から一歩を踏み出してください。
[執筆者]

澤口達也先生
医師、医学博士。
豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック院長。
糖尿病専門医として、日々、糖尿病や肥満症、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の患者さんの診療に従事し、食事指導や運動指導で数多くの方の減量を成功させている。
自身でも様々な食事療法やトレーニングを実践しており、過去にはアスリートフードマイスターや加圧トレーニングインストラクターの資格を取得。
また現在、健康スポーツ医、格闘技イベントでのリングドクターとしても活動している。
豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック
https://sawagucci.com/