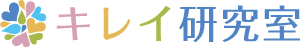だるさの正体は?疲労感の要因と日常でできる対策についてクリニック院長の菊池先生にお伺いしました
だるい、疲労感がある、やる気が出ない・・・年中疲れが取れないという方は多いと思います。
今年も残暑が厳しく、夏バテの影響もあるかもしれません。
でもその「だるさ」、ただの疲れではないかもしれません。今回は、慢性的な疲労感の背景にある医学的な要因と、日常生活でできる対策について、用賀きくち内科肝臓・内視鏡クリニック 院長の菊池真大先生にお話を伺いました。

疲労感の背後にある病気は?
だるさは、単なる疲れではなく、さまざまな健康問題のサインであることがあります。
以下に、医学的に関連が深い疾患とその特徴をまとめました。
1)酸素供給が不足し、全身がだるくなる
めまい、顔色不良、動悸:貧血(鉄欠乏性貧血など)
2)エネルギー代謝が乱れ、疲れやすくなる
喉の渇き、頻尿、体重減少:糖尿病
3)代謝が低下し、慢性的なだるさが出る
むくみ、冷え、体重増加:甲状腺機能低下症
4)精神的な不調が身体症状として現れる
気分の落ち込み、無気力、睡眠障害:うつ病・適応障害
5)睡眠の質が低下し、日中に強いだるさを感じる
いびき、起床時の頭痛、集中力低下:睡眠時無呼吸症候群(SAS)
6)原因不明の強い疲労が6ヶ月以上続く
筋肉痛、思考力低下、日常生活困難:慢性疲労症候群
7)ホルモン変化により心身の不調が出る
のぼせ、イライラ、不眠:更年期障害
8)解毒機能の低下で全身の疲労感
黄疸、食欲不振、尿の色変化:肝疾患(肝炎・肝硬変など)
だるさと一言でいっても、その症状は多岐にわたります。
だるさとその随伴症状で判断することになります。
内科では血液検査・ホルモン検査などが診断の手助けになることが一般的です。
なぜだるくなる?原因を見極めるポイントはだるさを感じる時間!
原因を見極めるポイントの一つとして、時間帯のよる特徴があります。
〇朝に強いだるさ
・起きるのがつらい、午前中は無気力だが午後に少し回復する:うつ、自律神経障害
・熟睡できず、朝から疲労感が残る:睡眠時無呼吸症候群
・朝の冷え・むくみ・だるさが目立つ:甲状腺機能低下症
・朝から強い倦怠感があり、日中も改善しない:慢性疲労症候群
〇午後〜夕方に強いだるさ
・活動後にエネルギー切れを起こしやすい:鉄欠乏性貧血・低血糖
・食後に強い眠気やだるさが出ることがある:糖尿病・インスリン抵抗性
・水分・ミネラル不足で午後にパフォーマンス低下:栄養不足・脱水
〇一日中続くだるさ
・休んでも改善せず、常にだるい:慢性疾患(肝疾患・腎疾患・自己免疫疾患など)
・ 微熱・食欲不振・体重減少などを伴うことも:がん・感染症の初期症状
いつ、なぜ、だるさが起こっているのか?
医師はこうした疾患を頭に描きながら、患者さんの診察に当たります。
疲労感やだるさから抜け出すためのセルフケア
病気には至らない疲れの状態もあり、日常の工夫で改善できることがあります。
1:質の良い睡眠をとる
ノンレム睡眠(深い眠り)をしっかり確保すると、細胞修復やホルモン分泌が促進されます。
寝る前のスマホや強い光は避けて部屋を暗めにする、起床・就寝時間を毎日そろえ、体内時計を整えることが大切です。
2:呼吸とリラックス
深呼吸を習慣にすると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。
腹式呼吸や「吹き戻し」をつかった呼吸トレーニングなどもおすすめ。
3:栄養バランスの良い食事
疲労回復に必要な栄養素は以下のとおりです。
・ビタミンB群(豚肉・豆類)→ エネルギー代謝を助ける
・たんぱく質(鶏むね肉・魚)→ 筋肉修復
・マグネシウム・鉄分 → 神経や筋肉の疲れに有効
不足しないよう、バランスの良い食事を心がけましょう。
4:湯船につかる
38~40℃のぬるめのお湯に15~20分ゆっくり浸かるのが理想です。
副交感神経が刺激されて、心身ともにリラックスできます。
5:軽い運動・ストレッチ
ウォーキングやヨガで血流を促進し、疲労物質の排出をサポートしましょう。
運動後は、睡眠の質の向上も期待できます。
6:マッサージやセルフケア
筋肉の緊張をほぐすことで、血流改善&リラックスできます。
肩こりや頭痛がある場合は、意識的にケアをしましょう。
このように、日常生活を送る上でのポイントもさまざまです。
できるところから始めてみましょう。
特に気を付けるべきサーカディアンリズム(概日リズム)って?
残暑が続く今、外出や運動が制限され、筋力や代謝の低下が懸念されます。
そこで注目したいのが、サーカディアンリズム(概日リズム)です。
これは、私たちの体内に備わった「約24時間周期の生体リズム」で、睡眠・覚醒・体温・ホルモン分泌・血圧・代謝など、ほぼすべての生理機能に影響を与えています。
ずばり、サーカディアンリズム(概日リズム)を意識して生活することが重要です。
早朝に人間の体は、メラトニンと呼ばれる睡眠ホルモンの分泌が低下し、体温が低い状態で目覚めます。
交感神経に切り替わる午前中に日光を浴びることでセロトニンといういわゆる「幸せホルモン」が分泌され活動量が上がり、夕方には体温や筋力のピークを迎えます。
夜間はメラトニン分泌と共に副交感神経が優位になり眠気が増してきます。
このサーカディアンリズムは動物・植物・菌類などほぼすべての生物に存在し、進化的には紫外線によるDNA損傷を避けるために獲得された生理現象なのです。
概日リズムを活かしてだるさ克服!
こうした概日リズムを活かして、疲労感やだるさから抜け出す方法があります。
「早朝の汗腺刺激」と「夕方の筋骨格刺激」を意識した分割トレーニング法を提案します。
人類はサルから進化する過程で、体毛を減らし、全身にエクリン汗腺を発達させることで、長時間の運動と暑熱環境への適応を獲得しました。
草原での狩猟生活では、早朝の涼しい時間帯に活動を開始し、発汗によって体温を調整しながら長距離を移動する能力が生存に直結していました。
文化的な背景からも、日本の農村部では、昔から「朝の涼しいうちに畑仕事を済ませる」という生活習慣があり、朝の発汗=活動開始の合図として機能していました。
汗は「労働の証」として宗教的・社会的意味も持ち、身体と環境の関係性を象徴するものでした。
一方で、江戸時代の武士階層では、夕方に剣術・弓術・馬術などの稽古を行う習慣があり、下肢や上肢の発達が夕方の活動と関連しています。
夕方は体温が高く、筋力発揮能力がピークに達する時間帯であり、技術的・力学的な運動に適していたと考えられます。
残暑期は、
朝:軽い運動で汗腺を刺激し、暑熱順化を促す
夕方:筋力トレーニングで筋骨格系を活性化する
このように、サーカディアンリズムを意識することで、自律神経も安定化し、疲労感改善に繋がります。
慢性的な疲労感やだるさは、単なる「体の不調」ではなく、私たちの生活リズム、環境、そして心の状態を映し出す鏡のような存在です。サーカディアンリズムを意識することは、現代の疲労社会において、最も根源的なセルフケアのひとつかもしれません。
(本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。)
執筆者

菊池真大先生
用賀きくち内科肝臓・内視鏡クリニック院長
慶應義塾大学医学部卒業
東海大学医学部客員准教授
米国ペンシルバニア大学消化器内科元博士研究員
日本アルコールアディクション医学会理事
日本総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内視鏡学会専門医、日本人間ドック健診専門医、日本病態栄養学会専門医、日本抗加齢医学会専門医
2024年秋、メタボとロコモを同時予防管理する未来志向型クリニックを東京・用賀の地に開業。
用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック
https://www.youga-naika.com/