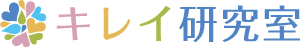五月病ってどういうもの?規則正しい生活を送ることがおすすめの対策です。
楽しかった連休もあっという間に終わり、戻ってきた日常・・・。
なんか疲れる、やる気が出ない・・・と思っている方は、もしかすると五月病かもしれません。
五月病ってどういうもの? どう対策すればいいの?
今回は、保健師の本田さまにお話を伺いました。

4月から新年度を迎え、就職・転勤・異動など、新しい生活がスタートした方も多いのではないでしょうか。
そのように慌ただしく過ごすなかで5月の大型連休が過ぎると、なんだかやる気がでない、会社に行きたくないと感じる方はいませんか。
今回は、そんな新生活に慣れ始めた5月頃にやってくる「五月病」といわれる身体の不調について、そしてその対処方法についてお話しします。
五月病ってどういうもの?
まずは、「五月病」について説明します。
五月病は医学的な病名ではなく、新しい生活や仕事環境のストレスにより身体に不調が現れる状態をいいます。
五月病と呼ばれる理由は、4月末から5月初旬にかけての大型連休が終わった頃に、体調が悪くなったり、気分が落ち込んだりするためです。
特に4月に社会人生活がスタートした新入社員や、異動や転勤などで職場環境が変化した方は、5月~6月のちょうど今頃に「五月病」の症状に悩まされる方も多いです。
五月病の原因
では、どうして5月に心身の不調を訴える人が多くなる傾向にあるのでしょうか。
新しい年度を迎えた4月は、仕事内容や人間関係の変化に伴い、心身共にストレスを受ける場面が多くなります。
特に新しい職場環境になると気持ちも引き締まり、「精一杯頑張ろう!」と意気込む方も多いですよね。
4月末から大型連休に入ると、やっとリフレッシュできますが、連休が明けるとまた仕事が始まります。
連休明けは、休暇中の生活とのギャップを感じやすくなり、「会社に行きたくない・・・」とやる気が出なかったり、気分の落ち込みに繋がったりしてしまうことがあります。
また、4月から蓄積した疲れが身体症状として出現することもあり、その結果5月の大型連休明けに心身の不調を訴える人が多くなる傾向にあります。
また、急に暑い日が続くなど、気候の変化も影響があります。
五月病の症状
五月病は病気ではないですが、一般的には「抑うつ状態」に近い症状が現れるといわれています。
・身体の症状
眠れない、 動悸がする、 疲れやすい・疲れがとれない、食欲がない、 頭痛や胃痛がする、朝起きられない
・心の症状
不安や焦燥感がある、 何をするにもやる気が出ない
イライラする、 好きなものに興味・関心が湧かない
これらの症状に一つでも当てはまる場合は、五月病の可能性があります。五月病の多くは一過性の症状で済みますが、何か月も続く場合は適応障害やうつ病などの病気の可能性があります。
「五月病」の対策のためにできること5つ
五月病の対策には、なるべく身体の疲れやストレスを溜めないように過ごすことがポイントです。
そのために自らできる5つの対策をご紹介します。
1.規則正しい生活を心がける
規則正しい生活は、血圧や呼吸など、身体の機能を自動的にコントロールする「自律神経」の働きを整えます。
そのために、食事や睡眠はなるべく規則的にとることが大切です。
朝食を抜くと日中の倦怠感や集中力の低下に繋がり、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼすといわれています。
食事は基本1日3食とるように心がけましょう。
睡眠時間はその日の体調や状況によって、個人差があります。
起床時の目覚めの良さや、日中の眠気、疲労の蓄積をもとに、自分自身に必要な睡眠時間を把握しましょう。
2.日光を浴びる
光を浴びることは、1日の生体リズムを調整する「体内時計」や「気持ちの安定」に大きく影響します。
日中に光を浴びずに生活していると、睡眠や覚醒のリズムが乱れ、徐々に身体に不調が現れます。
まず、朝起床した際はカーテンを開けて日光を浴びましょう。
日光を浴びることで睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が減り、脳が覚醒します。
そして夜になると暗くなるためメラトニンの分泌が増え、自然と眠くなり寝つきがスムーズになります。
日中に日光を浴びることで「セロトニン」というホルモンの分泌も増えます。
セロトニンは幸せホルモンともいわれ、脳の興奮を抑え精神を安定させる働きがあります。
また、セロトニンはメラトニンの原料でもあるため、日中に光を多く浴びると夜間のメラトニンの分泌が増え、睡眠の質も良くなります。
ただし、日光を浴びる際は紫外線の浴びすぎにも注意が必要なため、何時間も直射日光に当たるのは避けましょう。
また、紫外線対策も併せて行うようにしましょう。
3.適度な運動を行う
運動には心身をリフレッシュさせる効果があります。
ウォーキングやストレッチなど、可能な範囲で日々の生活に取り入れてみましょう。
運動後に、気持ちがすっきりとしているか、楽しめているか。
激しい運動をする必要はなく、適度に負担なく続けられることが大切です。
4.ストレスから距離をおく
休日は、一時的にストレス源から離れることで、身体や心の負担を減らすことができます。
趣味に時間を費やしたり、新しいことに挑戦してみたりするのも良いでしょう。
映画鑑賞や読書、ラジオや音楽を聴くなど、自分が楽しくリラックスして過ごせる方法を探してみましょう。
5.誰かと話す機会をつくる
悩みや不満を自分だけで抱えていると、悶々とすることはありませんか。
そんな時は、友人や家族に言葉に出して話してみると、自分の思いも整理され、悩みの解決のきっかけになるかもしれません。
人と交流することで気分転換にもなり、イライラや不安な気持ちを落ち着かせることができます。
五月病かもしれないと思ったら
なんとなく「五月病かも・・・」と思った方は、まずはこれまでに紹介した5つの対策を行ってみましょう。
それでも気持ちの落ち込みや、夜眠れないなどの身体の不調が続く場合は、周囲の人や、会社の産業医に相談してみましょう。
五月病は決して珍しい身体の不調ではなく、誰にでも起こりえます。
治療が必要な場合は、早期に治療を開始することで早期回復に繋がります。
ひとりで悩まず、周囲の人に相談し、早めに受診するようにしましょう。
執筆者

本田和樹
株式会社エムステージ産業保健事業部
保健師業務マネージャー
看護師として急性期精神病院で5年間勤務したのち、2020年エムステージ入社。
産業保健師の業務委託事業立ち上げに携わり、現在は複数の企業で保健師として実務をおこなう。
労働と精神衛生についての啓蒙活動、寄稿などもおこなっている。
取得資格:保健師、看護師、養護教諭一種、第一種衛生管理者等
株式会社エムステージ『産業保健トータルサポート』
https://sangyohokensupport.jp/