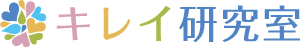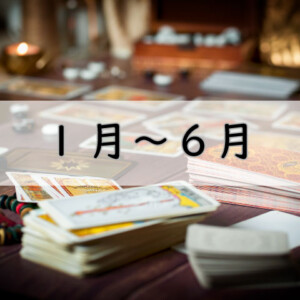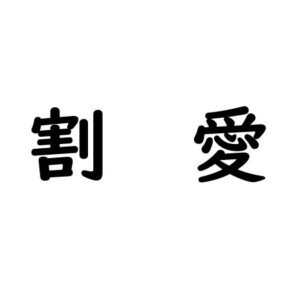【熱中症対策】水分摂りすぎは良くないって本当?SO.グレイスクリニック院長の近藤惣一郎先生にお伺いしました
今年の夏も、猛暑が予想されています。
熱中症を気にされている方も多いと思いますが、実際に何をどうすればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、熱中症についてSO.グレイスクリニック院長の近藤惣一郎先生にお話を伺いました。

真夏でなくても気を付けたい、熱中症について
今年も暑い季節がやって来ました。
活動的になり、楽しいイベントも盛りだくさんの夏ですが、高温・多湿への備えや注意を怠ると熱中症になってしまいます。
熱中症の発症機序、予防や応急処置について正しい知識を身につけ、日頃から十分な備えをしてゆきましょう。
熱中症は、日頃元気な自分には関係ないと考える人が多いかもしれません。
しかし、暑い日、蒸し暑い日に、喉の渇きと共に、立ちくらみや体のだるさ、イライラ感、頭痛を感じる時がありますね。
これは紛れもなく熱中症のサイン。
早めの対処を怠ると、誰でも「虚脱感」から「意識障害」といった重篤な状態に陥ってしまうこともあります。
また、熱中症は7月下旬から8月の真夏に起きると考えがちですが、体が未だ暑さに慣れていない梅雨時期でも、気温が急上昇したり、普段とは違う環境に身体がさらされると発症します。
特に今年は梅雨時期から気温が高い日が多いので注意が必要です。
どうして熱中症になるの?
熱中症とは高温環境下で体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻して発症する障害の総称です。
死に至る可能性のある病態ですが予防法を知っていれは防ぐことができます。
また応急処置を知っていれば救命できます。
1)なぜ熱中症になるの?(メカニズム)
人は36〜37℃の狭い範囲で体温を調節している恒温動物です。
生命を維持するための代謝や酵素の働きからみてこの温度が最適な活動条件なのです。
ですから私たちの体には、異常な体温上昇を抑えるための効率的な調節機構が備わっています。
熱を冷ます方法は2つあります。
一つは皮膚の血管を拡張し、熱を含んだ血液から外気に熱を逃がすこと。
そして、もう一つは汗をかき、汗の蒸発に伴う気化熱を体から奪うことです。
暑い時には、自律神経を介して末梢血管が拡張します。
皮膚には多くの血液が分布し、外気への「熱伝導」による体温低下を図ることができます。
また汗をたくさんかけば「汗の蒸発」に伴って気化熱が体から奪われ体温低下に役立つのです。
ただ暑さによって生じるこの血液分布変化や汗によって失われる水分や塩分に対して、私たちの体が適切に対処できないと、筋肉のこむらがえりや失神(いわゆる脳貧血:脳への血流か一時的に滞る現象)を起こします。
そして、熱の産生と熱の放散とのバランスが崩れてしまえば、体温が著しく上昇します。
このような状態が熱中症です。
2)熱中症をどのように予防すればいいのか
炎天下や屋外でなくても、高温や、風通しの悪い室内で熱中症は起こりえます。
積極的にエアコンを活用して室温を下げると同時に風通しを良くしましょう。
エアコンが体に良くないと決めつけるのは間違いです。
極端な低温設定にせず、直接風を受けるのではなく、空気を循環させる目的で使えば、熱中症対策に非常に有効になります。
設定温度は27~8度といったやや高めを奨励する説もありますが、これより低くても自分や周りの人が、ストレスなく快適に感じる温度・風力設定を行えば良いと考えます。
そのあたりは、状況に応じ、臨機応変に対応することが大切だと考えられます。
屋外では風通しが良く熱を逃がし、汗を速乾させる服装を着用しましょう。
熱中症対策としてはマスクは屋外では、よほどの理由がない限りは外したほうが良いです。
水分とナトリウム(塩分)が補給できる飲物や食べ物を意識して摂りましょう。
日陰や風通しの良い場所で、定期的な休憩をとることも大切です。日傘は日光を遮り、体感温度がグンと下がるので熱中症対策には有効ですが、普通の傘でもOK。
近年多い夕立、にわか雨時にも役立ちます。
屋外で過ごすイベントがある場合、日頃屋外に出る機会が少ない人は、数日前から早起きと併せ、30分程度のジョギングを行い汗をかくことで、身体が暑さに慣れてきます(暑熱順化)。
すると、汗から失われる塩分も減り、サラサラの汗をかけるようになります。
水分飲料の摂り方は早め早めが原則。喉の渇き、身体のだるさは、脱水症を知らせているサイン。
立ちくらみやクラクラ感、身体の火照りを感じた時点から飲み始めるようでは遅いのです。
周りにボトルを置くか、専用ケースで身につけて、喉の渇きを感じたら一回あたり50mlほどを、まめに、ちょこちょこ飲みましょう(一度に300ml以上は飲まない)。
トイレが近くなることを気にして飲まないことは危険です。
スポーツ飲料は血液、体液のバランスを最適に補正するので、真水やお茶と違い、汗をかく環境では、尿量を増やしません。
また冷たい物はお腹が冷えて身体に悪いと思われがちですが、熱中症対策に適した飲物は5〜15℃。
冷水は胃に留まる時間が短く、速やかに小腸に移動し、吸収されます。
口もとから胃、腸を冷やせば深部から体がクールダウンして精神的、気分的にも爽快感が得られます。
冷温を長時間保てるハイドレーションボトルや保冷機能が備わったボトルケースを活用することをお勧めします。
水分摂りすぎは良くないって本当?
「水分を摂り過ぎると、汗をかき過ぎ体がバテ、かえってよくない」というのは間違った考え方です。
体温を下げるためには、汗が皮膚表面で蒸発して身体から気化熱を奪うことができるように、しっかりと汗をかくことがとても重要です。
汗の原料は、血液中の水分や塩分ですから、体温調節のためには、汗で失った水分や塩分を適切に補給する必要があります。
暑い日には、知らず知らずにじわじわと汗をかいていますから、身体の活動強度にかかわらずこまめに水分を補給しましょう。
特に、湿度が高い日や風が弱くて皮膚表面に気流が届かない条件の下では、汗をかいても蒸発しにくくなり、汗の量も多くなります。
その分、十分な水分と塩分を補給しましょう。
また、人間は、軽い脱水状態のときには、逆にのどの渇きを感じにくくなってしまうのです。
特に高齢者にはその傾向があります。
そこで、のどが渇く前あるいは暑いところに出る前から水分を補給しておくことが大切です。
なお、どのような種類の酒であっても、アルコールは尿の量を増やし体内の水分を排泄してしまうため、汗で失われた水分をビールなどで補給しようとする考え方は誤りです。
一旦吸収した水分も、それ以上の水分がその後に尿で失われてしまいます。
またノンカロリーと称する人工甘味料入りの飲料水は、多量に取ると下痢を起こしやすいことも、是非知っておいて下さい。
日常生活で摂取する水分のうち、飲料として摂取すべき量(食事等に含まれる水分を除く)は1日あたり1.2リットルが目安とされています。
また、大量の発汗がある場合は水だけでなく、スポーツ飲料などの塩分濃度0.1〜0.2%程度の水分摂取が薦められます。
血液中の塩分が少なくなってくると倦怠感や手脚の筋肉のこわばり、こむら返りが起こります。こんな時は、失われた塩分を飴やグミでも補給できます。

熱中症予防に効果的な飲料温度は5〜15℃です。
最近は保冷力に優れるハイドレーションボトルが販売されており、氷をしっかり入れておけば、一日中冷たい飲物が摂取できます。

応急処置や、危険な予兆など
脈拍や呼吸回数の増加、顔色の蒼白感、唇のしびれ、軽いめまいといった初期の熱中症症状が起こったら、この時点で、十分な水分と電解質補給を行い、風通しの良い場所で、脚を高めにして横になり首や頭部、脇などを氷や冷水タオルなどで冷し熱中症の進行をくい止めます。
これを我慢して同じ状況で頑張っていると、熱中症が進行し、頭痛や嘔気、嘔吐などが加わってきます。
不幸にもこれ以上進行するとショック状態となり意識を無くしてしまうことになります。
この時の処置はやはり脚を高めにして横にして、衣類を緩め、とにかく体を冷却、必要によっては人工呼吸を行います。そして、119番で救急車を呼びましょう。
高齢者、肥満者、普段運動をしない人、暑さに慣れていない人、糖尿病・高血圧・心臓疾患等で薬を服用している人、無口で引っ込み思案の人、我慢強い人などは熱中症になりやすいので、自分だけのことでなく、自分の周りの人の体調を把握して、早めのアドバイス、対処を心がけてください。
今年の夏も猛暑となり、熱中症には注意が必要です。
熱中症は、防ぐことができるので、予防を意識してこの夏を過ごしてみてくださいね。
[執筆者]

近藤惣一郎(ロンリー侍ドクター)
SOグレイスクリニック院長
昭和63年京都大学医学部卒
医学博士(京都大学)
日本美容外科学会専門医
日本脳神経外科学会専門医・評議員
若返り専門の美容外科医。
「美は健康の上に成り立つ!」をモットーに、自らもダンサー・プロ沖釣り師として活動中。
SOグレイスクリニック
https://so-graceclinic.com/