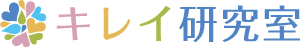肩が痛い。四十肩・五十肩の見極めとセルフケアについてクリニック 院長の中澤先生に伺いました
「肩が痛い」「上がらない」・・・といった悩みを抱えている方は意外と多いもの。
いわゆる『四十肩・五十肩』について、なかざわ腎泌尿器科クリニック院長の中澤佑介先生にお話を伺いました。

四十肩と五十肩、違いはある? どんな症状があるの??
四十肩と五十肩に大きな違いはなく、同じ疾患を指す日常語です
好発年齢が40〜60歳のため、それぞれの年齢に合った名称で呼ばれているものと思われます。
典型は痛みを伴う肩関節可動域の制限(外旋制限が顕著)で、受動可動域も落ちるのが特徴です。
「ひどい肩こり」と思ってしまう方もいますが、単なる筋疲労性の「肩こり」とは異なります。
原因は明確でない方が多く、糖尿病や甲状腺疾患、長期不動などがリスクを高めることが分かっています。
痛みが強い場合、夜間痛で眠れないことも。
たかが「四十肩」と思わないことが大切です。
放っておけば治る?どこに相談すればよい??
従来は自然軽快するといわれてきましたが、数年後も可動域への影響が残る例が一定数あります。
早期の痛みコントロール+可動域の維持が推奨されます。
まず整形外科(もしくは肩を診る医療機関)へご相談ください。
X線やエコーで腱板断裂・石灰沈着など他疾患を鑑別してくれます。
理学療法(関節モビライゼーション、肩甲帯・回旋筋腱板の協調訓練)は有効です。
また、関節内ステロイド注射は短期的な痛み軽減に有効とされています。
関節拡張術(ハイドロダイラテーション)は痛みと機能の改善に役立つ報告が増えています。
カイロプラクティックや鍼灸を補助的に選ぶ人もいますが、標準治療の代替にはなりません。
安全性と医療連携を最優先に。
※鍼灸に関しては医師が代替治療として必要と判断した場合医療保険が使えることもあります。
おすすめのセルフケア(痛みの段階に合わせて)
(1)急性〜凍結初期(痛みが強い時期)
無理な強圧ストレッチは避けましょう。
温罨法+鎮痛薬もありますので、痛みが強いときなどは、医師や薬剤師と相談してください。
荷重の少ない可動域維持のため、エクササイズもおすすめです。
ペンデュラム(振り子)運動やテーブル滑り(前方・外転方向へ体幹を倒す)といったものがあります。
解説している動画もありますので、医師に相談しながらおこなってみてください。
(2)慢性期(痛み落ち着き、固さが主体)
痛みが落ち着いているときは、積極的にエクササイズやトレーニングをおこないましょう。
棒(タオル)外旋・外転エクササイズ)や 肩甲骨周囲筋(前鋸筋・下部僧帽筋)と回旋筋腱板の協調トレーニングがおすすめです。
痛みがあるときは無理せず、心地よくできる範囲でおこないましょう。
日常生活を送る上でのコツをご紹介します。
夜間痛対策
横向き時は痛い肩を上にし、抱き枕+肘下に枕で楽な肢位をつくりましょう。
デスクワーク対策
肘は体側に近づけて肩をすくめないようにしましょう。
こまめに可動域リセットします。
市販薬やサプリは?
炎症や痛みを抑える薬は市販薬でもあります。
外用NSAIDs(貼付・ゲル)やアセトアミノフェン/NSAIDs内服が一般的です。
ただし、長期連用は副作用に注意が必要です。
痛み止めを飲んでも痛みが消えない、飲み続けないと日常生活が送れないといった場合には、市販薬を飲み続けるのではなく、医師にご相談ください。
また、サプリメントは有効性の確立したものは乏しいのが現状です。
飲みたいものがある場合は、一度かかりつけ医に確認してみましょう。
35歳でも四十肩になるの??予防は?
多くはありませんが、30代でも四十肩になる肩はいます。
残念ながら、四十肩や五十肩の明確な予防法はありません。
しかし、血糖管理、肩を固めない生活(長期の固定を避け、痛くない範囲で動かす)が現実的です。
まとめ
四十肩・五十肩は痛みのコントロールと可動域の維持が肝心です。
段階に応じた理学療法+必要に応じ注射治療で、回復を前に進めましょう。
四十肩や五十肩は軽く見られがちですが、QOLにも大きな影響を及ぼします。
受診の目安としては、夜間痛が強い、日常生活に支障、数週間で改善がない、外傷後に急に腕が上がらなくなった、発熱・全身症状を伴うなどがあります。
糖尿病・甲状腺疾患のある方は早めの受診をおすすめします。
参考文献(主要エビデンス)
JOSPT CPG Shoulder Pain and Mobility Deficits: Adhesive Capsulitis(2013)
NICE CKS Shoulder pain – Frozen shoulder(最新版の要点)
AAOS OrthoInfo Frozen Shoulder (Adhesive Capsulitis)(患者向け解説)
Wong CK, et al. 自然経過の“完全治癒”は一様でないことを示した系統的レビュー(2017)
Chen T, et al. ハイドロダイラテーションの有効性(メタ解析、2024)
Sun Y, et al. ステロイド注射と理学療法は同等の効果(メタ解析、2016)
Vita F, et al. 早期診断と治療戦略(レビュー、2024)/最新のBESS患者経路ガイド(2025)
(注)本記事は査読論文とガイドラインに基づき専門医が監修しましたが、個々の症状には個別の評価が必要です。自己判断での強い矯正や過度なストレッチは避け、必要時は医療機関にご相談ください。
※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。
執筆者
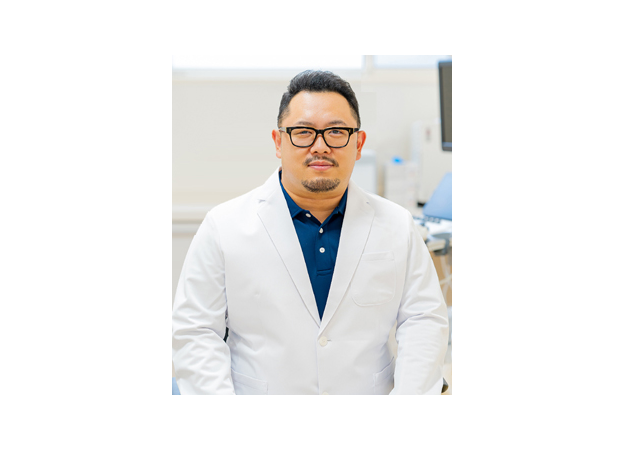
中澤佑介(なかざわ ゆうすけ)先生
金沢医科大学医学部医学科卒業。
「患者さんに近い立場で専門的医療を提供したい」という思いで2021年、なかざわ腎泌尿器科クリニックを開設。
2024年9月、JR金沢駅前に金沢駅前内科・糖尿病クリニック(https://kanazawa-naika.jp/)を開院。
なかざわ腎泌尿器科クリニック
https://www.nakazawa-cl.jp/